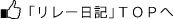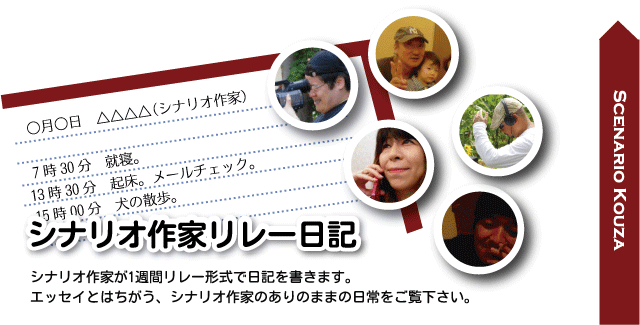2009年3月10日(火曜日)
今日は娘(7歳)のバレエの稽古日で、愛車(もちろんチャリンコ)で稽古場まで送り迎えをした。貧乏人がバレエとは何事かと言われそうだが、四年前、何を血迷ったか嫁はんが勝手に申し込んでしまったので仕方がない。上の娘の時はピアノを習わせたので、下の娘にもまあ一つくらい習い事をさせてやろうという親心でもあったのだが、ピアノとはちがい、バレエは桁違いに金がかかる。ふだんはいいのだが、二年に一度発表会というのがあって、これに金がかかるのである。今年はその年にあたっていて、正直、私はとても悲しい。以前小さな劇団で舞台脚本や演出もやっていたので、舞台に何かと金がかかることはわかっているが、それにしても前座みたいにチョロッと出るだけでどうしてこんなに金がかかるのかと思う。まあ娘は楽しみにしているようなのでやめろとも言えないが、秘かにやめたいと言ってくれないかと思っている次第である。
ところでこの下の娘だが、子どもらしい素直さがみじんもない。上の娘は大学に入ってから反抗期を迎えるといった超遅咲きであったが、下の娘は小学一年生にして既に反抗期デビューを果たしている。なにかにつけてつっかかって、チンピラまがいの言い掛かりをつける。素直でないのは嫁はんに似たのだろうが、性格がねじけているのは私に似たのだろう。遺伝とはおそろしいものである。おまけに態度がでかい。度々私を指差して「な、わかるやろ。そう思わへんか?」とナニワのオバハンのごとくえらそうに同意を求めてくる。そんないかつい娘だが、反面、感受性が敏感な一面もある。
5歳の時、吉田山の節分祭に連れて行った。お参りをして帰る際、参拝者でごった返す中、参道で障がい者の人たちが障がい者自立支援法の撤廃を求めるとともに、募金活動をしていた。それを娘はジーッと見つめていたのだが、その時は何事もなかった。だが、帰宅して夕食を食べていると全く突然に、ワアッと声をあげて号泣したのである。聞けば今日見た身体の不自由な人たちが、どうしてあんな寒いところに立って働かなくてはいけないのかと、私に泣いて問い詰め訴えるのである。それはまさに幼き義憤であったのだが、恥ずかしながら私はまともな答えを見つけてやることもできず、不覚にももらい泣きするばかりであった。
つい五日ほど前にも帰って来るなり泣き伏した。聞けば、学童クラブの送別会で寸劇をやることになり、本人は出演すると言って真っ先に手を上げて選ばれ、得意満面張り切っていたのだが、いざフタをあけてみるとセリフは一つで、しかも役はその他大勢の一人だったのである。全員で一つのセリフを一斉に言う……我が娘がそんな屈辱に黙っていられるわけがない。ところがもっとおそろしいことに、その翌日には貴重なたった一つのセリフも削られてしまったと、帰って来るなりまた泣いて、風呂に入ってからも泣いて私に訴えた。どうやら学童クラブの先生方は娘を小学一年生とみくびり、納得する説明を怠っているらしい。(勘弁してえなもう)である。だが私は、(ここや、ここで父親たる威厳を見せつけなあかん)と思い直し、説得する言葉を色々と探して、「自分のセリフの数を数える俳優ほどあかんのやで」とか「そんなことでいちいち泣いてたらお父さんの仕事なんか毎日泣いてなあかんワ」とか「人の芝居を見るのも勉強や」とか言い募って慰めたが、娘は突如怒り出し、「そんな大人のむずかしいこと言うたって、子どもにわかるわけないわいッ」と一蹴されてしまったのである。父親失格、撃沈である。
先月、その娘を連れて私がホンを書いた教育映画を、神戸の小さな映画館まで観に行った。担当されたキャメラマンが亡くなり、その追悼上映会なのであった。そんなことでもなければ一般には眼にふれない映画である。娘も行くと言うので連れて行くことにしたのだが、電車に乗ってからちょっと後悔した。前に自作の舞台を見せた時、「何かようわからんかったワ。おもろなかった」と言われてガッカリしたことを思い出したのである。ましてやその前の週に『マンマ・ミーア!』を観て大感動し、「あれよかったワ。もいっぺん観に行こ」と言っていた娘である。そんなものと教育映画を比べられた日にゃ……。まあしゃーないかと思って連れて行ったのだが、映画を観ながら娘が声をあげて笑っているではないか。少しは笑えるシーンを作ってはいたが、監督が喜劇俳優でもあったので、笑いの部分をかなり誇張して演出をされていたのが幸いした。また、泣けるシーンもあり、笑って泣けるという、手前ミソながら教育映画の中では出色ではないかと秘かに思っている。(殆ドノ人ガ観ナイダロウカラ言エルコトダケレドモ)それで娘の評価というのが「まあまあおもろかったな」ということでホッとした。その上追悼上映会ということで監督とプロデューサーのトークショーがあり、私も名前を呼ばれて場内で挨拶したということもあり、娘が私を見る眼が俄然変わったのである。ふだんは私が売れない絵本を書いていると思っている娘は、何だかお父ちゃんが偉い人に感じられたのだろうか、ちょっと嬉しそうだった。帰宅後、宿題の“あのね帳”に、神戸に行って映画を観た話を書くというので、それとなく「お父さんのことは書かんでええさかいな」と言うと「書かへん」とあっさり言われてチョイと寂しい気がした。
昨日、学童クラブの寸劇のことが気になって、稽古をしてるのかと尋ねると、平気な顔をして、「もうあんなんどうでもええねん。練習もせえへん」と言うのである。
子どもならではの凄まじい切り替えである。正直、父親として、というより脚本家として見倣いたいと思った。いつまでも一つの作品にウジウジグチャグチャとこだわっていることのバカらしさである。何事も忘れるに限る。大人が子どもに学ぶべき点はたくさんあるのである。(今日はシナリオと関係ない話でスンマヘンでした)
今日は午前中ホンの直しをやって、午後からは企画書と当日記を書いておしまい。
ほなまた明日デス。
2009年3月11日(水曜日)
今日は午後と夜に打ち合わせがあった。日に二度も打ち合わせがあるなどというのは私にとって滅多にないことである。午後は某撮影所(京都には二つしかないので察しはつくだろうが)近くの喫茶店で東京から来られたプロデューサーとの打ち合わせである。断っておくとこのプロデューサーは東京からわざわざ私に会いに来たのではなく、撮影所に所用があって、ついでに声をかけてもらったのである。
さて、某撮影所の周辺にはいくつかの喫茶店がある。中でも映画関係者の御贔屓は、撮影所を出てすぐ、三条通り沿いにあるS店だろうか。この喫茶店のコーヒーは美味しいと評判で、とても流行っている。だがコーヒーの味もわからん、マイナー志向の私は、その近所にある無意味に暗い喫茶店の方に馴染みがある。馴染みがあるといえば何か哀愁のようなものを想像されるかもしれないが、ただ単にいつも空いているというのが馴染んでいる理由である。だがこの喫茶店は曜日や時間帯を考えて行かなくては大変なことになる。たまにナニワ風のオバ様方の巣窟となり、うるさくてとても打ち合わせどころではなくなるからである。いつだったか、打ち合わせ中にその魔の刻が訪れ、怒鳴りあうようにして打ち合わせをした覚えがあり、店を出た時には目眩がしたものだった。
昔、撮影所内で映画を学んでいた頃、近くの大映通りにコールマンという喫茶店があった。店内はとても広々としていて、グランドピアノやゆったり座れる豪華なソファや椅子があり、眼の大きな美人店長がおられた。私は度々ここで先生と会い、シナリオを批評してもらった思い出がある。本当は長居してはいけないのだけれど、先生と一緒だと三時間、四時間と話すことができた。コールマンという名はもちろんコールマン髯からとられたもので、店内には多くの映画関係者が訪れていた。
そのコールマンで、あるプロデューサーとTV時代劇の企画書について何度も打ち合わせたことがある。その頃はまだ右も左もわからなかった私は、そのプロデューサーの言われるままにプロットを直し続けた。今のようにパソコンもなく、手書きで、ペラ15枚くらいのものを20回ほど書き直しただろうか。その人は撮影所のプロデューサーで、TV局の人ではなかった。面白いと言っておきながら書き直せと言ったり、昨日言ったことが今日は変わっているといった理不尽なものだったが、私はシナリオまで行き着くことを信じて書き続けた。ある日、私はそのプロデューサーに呼び出され、製作会社の事務所に出向いた。彼はビールを飲みながら、私のプロットについてグダグダと言い始めた。そのうち、彼の話はプロットから大きく外れて、今かかわっているTV作品の製作費が減らされ、自分のギャラが半減したなどという愚痴に変わっていった。(その半減したという額はサラリーマンの平均的な給料をはるかに上回っていたが)。私にとってはどうでもいい話である。私は苛立ち、あなたはもういいのでTV局のプロデューサーと直接話がしたいと言った。すると彼は、「そんなもん十年早いわ」と吐き捨てたのである。私はキレた。何を言ったのか忘れたが、激しく怒鳴り散らして部屋を出て行ったことだけは覚えている。
そのプロデューサーの名誉のために言っておくと、TV作品ではちゃんとした実績があり、決して悪い人ではなかった。だが、愚痴が多いのと若い人に対する配慮が欠けていたのは確かだと思う。
そのプロデューサーは数年前に亡くなり、コールマンも今はもうない。懐かしいというより、何だか時間を浪費しただけだったような気もする。これを読んでおられる脚本家志望の方、プロデューサーには十分気をつけられたし。信用できるのはまず最初にギャラの提示をする(どのタイミングで入金するかも含めて)、その次には製作資金の裏付けを話す、それからスケジュールの話をする、最後には配給の話をするといったような人だろうか。いきなり作品に対する思いばかりを語って具体的プランのない人物は要注意である。映画をつくるということは夢でも何でもなくて極めて現実的なことだから、作品化されなければ全く意味がないからである。そこのところを冷静に判断されたし。まあプロデューサーで一番困る人というのは、すまんが金がない。これだけで書いてくれと正直に言う人だろうか。やりたくないけどやりたくなってしまうのである。
ともあれ、金でトラブりたくないなら、メジャーな映画かTVドラマをドシドシ書くべし。(尤も、それができれば苦労はしないが……)。
というわけで午後の打ち合わせで御会いしたプロデューサーはどうだったかというと、CSドラマの打診だったが……まずは製作出資元を含めたギャラの話。次に製作体制の話。そしてスケジュールの話。最後に作品に対する熱意、であった。見事合格!
というより、貧乏性の私は話があった時点で引き受けるつもりであったが……。
今日は午前中に企画書を書き、上記の通り午後の打ち合わせ後、夜からも打ち合わせ、というより祇園の美味しい鮨屋で食べて飲み、帰ってから当日記を書いておしまい。
ほなまた明日デス。
2009年3月12日(木曜日)
ゆうべは昨年から講師としてかかわっている、大阪にある専門学校の来年度のカリキュラムの打ち合わせをしたのである。もともとはミュージシャンや俳優を養成している学校なのだが、昨年新たに映画コースを立ち上げるというので日頃お世話になっている録音技師のH先生に頼まれ、シナリオを教えるようになったのだった。
教える、といえば聞こえはいいが、第1日目の日記にも少し書いたが、学生が私のような苦労をしないでもいいようにというのが第一で、反面教師のつもりなのである。そもそもシナリオなど人から教わるものではないというのが持論であるので、どうするかと考えたが、結局、新井一先生の初心者向け入門書に野田高梧先生の『シナリオ構造論』をミックスしたような形で自分なりにアレンジし、それに加えてサンプルシナリオや採録シナリオ、DVDも使いながら一年間教えた。尤も、脚本家志望の学生は一人もおらず、受講生は監督や俳優志望が殆どなので、どこまで教えればいいのかわからなかったが、書くことはともかく、何とかシナリオを分析して読めるまでにはなってくれたかと思う。
さて、私が映画を勉強していた時代とちがい、今はおそろしいまでにハードが進歩している。学生たちにしてみればビデオキャメラとパソコンさえあれば映画なんか簡単にできまっせという時代である。私が教えている学校でも、入学してすぐに作品(10分ものの短編)を作らせている。彼らは一生懸命に撮っているのだが、何かがちがうと思ってしまう。それはやはりフィルムで撮る時の緊張感がないということだろうか。ワンショットにかける、息をつめるような感覚はなく、ただただキャメラをダラダラと回している。
講師のA監督やOキャメラマンに聞いても、やっぱりフィルムからやらなあかんなというのが一致した意見だった。それで来年度からフィルムをやろうというわけで、16ミリを教える設備や場所を学校サイドに要望していたのだが、結局そのスペースが確保できないというので却下されてしまった。
まあ別にデジタルであっても映画は撮れるのだし、この先フィルムそのものが生き残るかどうかもわからないので、それはそれでいいのだが、映画の基本としてフィルムを教えるというのは必要なことなのではないかと思う。何が基本やと言われると困るが、これはもう理屈ぬきで必要なのだと言ってしまいたい気になる。
ペラの感覚というものがある。「ペラに書くという感覚というのは、そのままフィルムに焼きつけていくようなもんじゃないですかね」と以前友人から言われたことがある。そう言われてみればそうかもしれんと思う。サイレントの時代には特にそういう感覚であったのではないかと思えるフシがある。別にペラだから名作が生まれるというわけではないが、ペラの感覚を知らない世代の脚本というのは、どこか流れてしまってメリハリ、いい意味のひっかかりに欠けると思うのは偏見だろうか。
余談だが、伊丹万作の無声映画シナリオ『天下大平記』のファーストシーンを授業で分析したことがある。一行一行を読み解いてゆくと、僅かな枚数の中で主人公の性格が的確に語られ、やわらかな映画のムードも感じられてとても楽しい。何より、ポカンとぬけたような余白があって、これが時代劇特有の情緒、詩となってシナリオに滲み出ている。最近の時代劇にはこの余白がなく、物語と過剰な感情ばかりが押し付けられてしんどいものを感じる。
学生たちにこれを音読させたのだが、サイレントだと断っているのに、T(タイトル)セリフ部分を本当のセリフだと思い込んでいたことが面白かった。おそらくは彼らの頭の中には、色付き音付きの画が思い浮かんでいたのだろう。
フィルムの感覚とペラの感覚。これが映画的感覚を養う上で必要な気がしてならない。根拠は何もないので、古いと言われればそれまでだが……。
ゆうべの打ち合わせでは16ミリがダメなら8ミリではどうかと私は提案したが、画質や音の問題がネックとなり、それも却下となった。だが、そんなことを話していると、Oキャメラマンが突然声を張って言ったのだ、「けど、機材のことを何やかんや言うても、やっぱり脚本がちゃんとしてないと意味ないですよ」と。H先生もA監督も「それはそうだ。まずは脚本だ」と唸るように同意する。大ベテランの方々が原点に立ち返るように「脚本」と口にする。H先生は某有名私立大学の教授でもあるが、いくら脚本の重要性を訴えても、学校サイドにはなかなか理解されず、結局学生たちのつくるものはゲームかコントみたいなものにばかりなってしまうと嘆いておられた。当たり前のことなのだけれども、考えてみれば、その当たり前のことをないがしろにしている現状があるような気もする。
脚本に話が及び、自然と、視線は私の方に向いた。痛いなと思った。学生の話どころではない。何とかしなければいけないのは自分の方である……トホホ。
今日は午前から午後にかけて企画書を書き、その後当日記を書いておしまい。
ほなまた明日デス。
2009年3月13日(金曜日)
今日は企画書を仕上げて先方に送った後、やることが何もなくなってしまったので、以前に買って積んでおいた『タルコフスキイの映画術』(アンドレイ・タルコフスキイ著・扇千恵訳/水声社刊)を読んだのである。この本はタルコフスキイがモスクワにある脚本家・監督二年制高等クラスで講義した内容を中心に構成されている。
私はタルコフスキイの映画を特別に好きでも何でもないが、この本を読んで(すごいオッサンやな)と思った。正に芸術映画の権化である。映画のために生きた人である。このタルコフスキイの映画愛だけでも巨匠やなとわかる。
この本で興味深かったのは、タルコフスキイがシナリオ(脚本家)というものについて、どういう認識であったかということである。チョイと長いけれど一部を紹介すると……。
『プロとしての脚本家には悪いが、私の考えでは一般的にいかなる脚本家も存在しない。これは、映画とは何であるかを素晴らしく良く理解している作家か、あるいは自分で文学的資料を扱う監督かのいずれかである。なぜなら、すでに語ったように、文学においてシナリオといったジャンルは存在しないからである。』
『監督がシナリオを受けとり仕事を始めると、どれほどそのシナリオの構想が深いものであり正確に予定されたものであっても、何かを変更することを余儀なくされるのは常のことだ。彼は決して文字通り、鏡に映すようにシナリオを映像化することはできない。常に一定のデフォルメが行われる。それゆえ、監督と脚本家の仕事は、通常、闘いと妥協によって進められることになる。十分な価値のある映画が完成することも例外ではないが、それは脚本家と監督のあいだにあった最初の関係が作業中に崩れ去り、彼らの「廃虚」に新しい概念、新しい有機体が生じた場合である。
しかし、いずれにせよ、映画に対する作家の仕事の最も正常なバリエーションとは、最初の構想が崩れることもデフォルメされることもなく、有機的に発展していくとき、つまり演出家が自分のためにシナリオを書くか、あるいはシナリオの執筆者が映画を撮るか、いずれかの場合であると考えられる。
ゆえに、最終的に演出とシナリオの仕事というふたつの職業を切り離すことはまったく不可能に思える。完全なシナリオは監督によってのみ創作されうるか、あるいは、監督と作家が理想的な協力関係にあるとき、その結果として完成しうるのだ』
これじゃあ脚本家は添え物かと怒られそうだが、これはこれでタルコフスキイの本音であろう。なぜなら彼が目指したのは純然たる芸術なのであって娯楽ではないからである。あるのは己の意識だけであって脚本家や観客の意識などはどうでもよいのだ。それは次の言葉にも表われている。
『真の芸術は、観客にかなる印象を与えるかについて考慮しないものだ』
私は常々考えるところがあって、例えばタルコフスキーとかパラジャーノフとかキアロスタミとかアンゲロプロスとかゴダールなどといった、世界的に認められた監督にとって、シナリオというものはどういう位置付けなのかということであった。少なくとも日本のシナリオのスタイルで書かれたとして、それが読物として面白いものであったり、胸をうつものであったり、激しく何かを訴えかけてくるような気がしないのである。あくまで監督とセットで表現されるべきものという考え方になるのではないだろうかと思っていたのだが、タルコフスキイはそれに近い答えを出している。
それにしてもタルコフスキーはしつこく脚本家に対する嫌がらせかと思うような持論を展開する。
『率直に言えば、一般にシナリオの執筆やさまざまな編集会議でのシナリオの批評などは、すっかり流行遅れで、何か復古的なものであるとさえ言える。いつか映画は拒否されるだろう。なぜなら、絵(シャシン)をシナリオに従って統制することは不可能だからだ。それは一目瞭然である。莫大な数の映画が優れた映画への期待を込めて製作され始める。しかし、すべては失敗する。ところが、誰もシナリオに期待しなかった作品が、突然、傑作になることもあるのだ。このようなことはしばしば起こる。要するに、ここにはいかなる論理も存在しない。もしシナリオによってそれがどのような映画になるかを判断することができると誰かが考えるなら、それは大きな誤解である。』
何か脚本家に恨みでもあるような書きっぷりである。が、かといってタルコフスキイがシナリオ(脚本家)をないがしろにしているとは思わない。タルコフスキイを弁護するわけではないが、彼は決してシナリオがなくても映画が撮れるとは言っていないのである。実際、ゴダールだってフェリーニだって(おそらく他の作家たちも)、良いシナリオは喉から手が出るほど欲しかったのだ。タルコフスキイだって、脚本家は必要なくてもシナリオは欲しかったはずだ。実際、シナリオを使って撮っているのだから。百歩譲って彼らが、シナリオがなくても傑作を生み出したとしても、その頭の中には完璧なシナリオがあると思うのである。
『基本的に、映画ドラマツルギーは、素材の発展における音楽的形成に何よりも近く、そこで重要なのは論理ではなく、感情や情緒の変化である。論理的な連続性による動きであって、連続性そのものではない。論理や歴史ではなく感情の発展を探さねばならない。チェーホフは短編を書き終えたあと、最初の一ページを削除した。「なぜなら」という動機をすべて削除したのも決して偶然ではないのである。素材が「健全な意味」から解放されるときにこそ、自然な発展と変化の中で生きた感情が誕生する。撮影を終えた映画の素材が素晴らしいものであればあるほど、それは当初のドラマツルギーをたちまち断ち切ってしまう、ということはずっと以前に証明されていることだ』
けど、脚本家って、こういう部分を目指すもんとちゃうんかなあ。感情の発展なんてことを言っているんやから。
やっぱりタルコフスキイは監督だからこんなことを言うのであって、これが世界一流の脚本家であれば言わないはずだ。
そういえば依田義賢先生がこんなことを言われていたと思う。
『映画を一番最初にイメージするのは原作者でも監督でもありません。脚本家です』
タルコフスキイに聞かせたらどない言うのやろ。
(それでもこの本、頭が痛くなるけれど映画の教科書としてはすごく基本的なことが書かれていて、とても素晴らしいので、監督、脚本家志望の方にはオススメです)
ほなまた明日デス。
2009年3月14日(土曜日)
昨日も書いたが、一昨日に三年越しのホンをひとまず出し、昨日に企画書を出して、何もやることがなくなってしまった。東京在住の脚本家の方々の日記をチラと見ると、(やっぱりちゃうなあ)と思ってしまう。邦画バブルといわれるが、京都に住んでいるといったいどこにそんなもんがあんねんという感じで情けない思いがする。
時々、「(仕事もないのに)どうして京都にいるんですか?」とか「(仕事もないのに)地方(京都)は大変でしょう」とか言われることがある。放っといてくれと言いそうになるが、確かに今の京都では自らが立ち上がって映画を創ろうなどという姿勢は、全くないとはいわないがないに等しいといえる。
かつて京都の撮影所の経理課では、社員が金庫に札を足で突っ込みながら、「誰か使ゥてくれえ」と言っていた夢のような時代もあったそうである。それが今では美術向けの貸しスタジオみたいになって、殆どの映画やTV作品において、監督や脚本家、メインスタッフまでもが東京からやって来る。(もちろん企画製作も東京)
だから京都に住んでいても、撮影所からホンを書く仕事などは滅多に入って来ない。尤も、営業もしないのでそれは無理もない話かもしれないが。
私が京都に住んでいるのは深い理由はない。会社勤めを辞め、たまたま入った学校が京都の撮影所内にあった。そこの講師の先生方は大映京都のスタッフがメインで、自然と時代劇を基礎とする映画づくりを叩き込まれた。それまでは洋画に魅力を感じていた私だったが、それでいっぺんに時代劇が好きになってしまい、伊丹万作や山中貞雄、溝口健二、三隅研次といった監督たちに魅了され、京都に居着いてしまったのである。
時代劇が好きである。以前『月刊シナリオ』にも書かせてもらったが、溝口監督の『西鶴一代女』を場末の映画館で観て、身体がふるえてしまったのだった。元大映京都の幹部だったTさんにそれを話し、「あんな凄い映画をつくる監督と同じ会社で仕事をされてたなんて羨ましいです」と生意気なことを言うと、Tさんは露骨に嫌そうな顔をして、「ミゾさんにはどれだけ嫌な思いをさせられたか」と言うのである。Tさんは依田先生の原稿を取りに自宅まで行くのだが、家に引き込もって出て来られなかったのだそうである。言うまでもなく、それは「ミゾさん」のせいだというのだ。まあ確かに、溝口監督は「溝口殺してワシも死ぬゥ〜」とナグリを持ってスタッフから追い回されるなど、作品のためにスタッフに強いる犠牲は凄まじかったというが、あがったシャシンを観て、皆納得していたのである。恨み節を言ったTさんも最後には、「けど作品は素晴らしかったなあ」と吐息されたのである。
かつてのような本物の時代劇は、もうつくれないという人が多い。ある意味、それは正しいと思う。『浪人街』『椿三十郎』『隠し砦の三悪人』『百万両の壷』『眠狂四郎』『木枯らし紋次郎』『座頭市』といった作品が映画やTVでリメイクされているが、成功しているとは言い難い。やはり時代劇独特のムードというか情緒というか、理屈ではない詩的な部分において全く物足りない。
昔の時代劇の映画監督は、映画の原点である、光と影を表現することがうまかったと思う。伊藤大輔監督の『忠次旅日記』において、子どもたちが遊ぶその影をとらえているカットがあるが、そんな何でもない映像にも背筋がゾクリとなったりする。時代劇に現代的なテーマや社会的意義や理屈を持ち込もうとすると、かえって光と影の美しさが損なわれる。かつての優れた時代劇の中にあったのは、生きるか死ぬかであって勧善懲悪ではなかった。理屈ぬきに人間が生きているという純粋な形を表現するのが時代劇だったと思う。
時代劇が京都から生まれなくなりつつある今、そうした光と影を表現するために積み上げられてきた伝統が滅ぶのは、最早時間の問題となってしまった。伝統どころではなく、撮影所そのものの存続も危ぶまれている。だが一部の人はその危機を何とか脱したいと、模索しているのも事実である。そうした人たちに頼まれ、私も昨年末から数本の時代劇の企画書を書いた。
一昨日ひとまずあげた三年越しのシナリオも時代劇だが、地方のある会社社長が発案者であり製作者である。この社長は前回の時代劇を製作するにあたり、出資を求めて地元企業を100社まわったという。それまでは映画界とは全く無縁の方だった。もちろんビジネスという側面もあるが、何より地元には優れた人物がたくさん出ている、それを映画にしたいという強い思いがあった。そうでもなければリスクをおかしてまで数億という金を集めて映画などつくれないだろう。
こうした製作者が京都にあと3人もあれば、時代劇は救われるだろうなと思う。たかが時代劇。そないたいそうなと言われそうだが、時代劇を基礎として映画を学んだ者としては意外に切実なる問題なのである。
ほなまた明日デス。
2009年3月15日(日曜日
)
今日は日頃お世話になっているプロデューサーの事務所の引っ越しを手伝ったのである。ペンより重いものを持ったことがない者が無理するなと嫌味を言われながら、何とか戦力として働いた、と思う。
というわけで、これで一週間が終わった。こうして書いてみると自分がいかに映画(シナリオ)の中に入り切れず、外から眺めているかというのがわかって、いいかげんなもんやなと思う。良いシナリオを書かなければえらそうに何を言っても意味はないのである。
最後なので、私が今までに読んだ中でシビれたシナリオ、(こんなんが書けたらええな)というものをあげておきたいと思う。
『元禄十六年』(作・八尋不二)
『渡辺華山』(同上)
『無法松の一生』(作・伊丹万作)
『手を振る機関車』(作・犬塚稔)
『パイナップル部隊』(作・小国英雄)
『祇園の姉妹』(作・依田義賢)
この他にもたくさんあるが、これらの作品が印象深いのは、若い頃にすべて写経(書き写した)したシナリオだからということもある。シナリオを勉強されている方も、一度は共感したシナリオを写経してみてはどうかと思う。それが役に立つかどうかはわからないが、作品の構造はよく理解できるはずである。
これらそれぞれのシナリオに対する思いなどは敢えて書かない。こんな古いシナリオをあげるなどというのは、それこそ時代遅れなやつだと言われるかもしれない。だが、好きなものは仕方がないのである。
笠原和夫さんはその著書『映画はヤクザなり』(新潮社刊)中の“秘伝 シナリオ骨法十箇条”の最後にこう述べられている。
『一番大切なことは骨法などに捉われて、自分の「切実なもの」を衰弱させてはならない。わたしも駆け出し時代は、二、三日徹夜して一気に一本仕上げたものである。骨法なんて、まだ考えもしなかった、知りもしなかった。それでちゃんと映画になったし、商売にもなった。その中で腕も磨かれたし、感性も鋭くなったと思う。若い人はガムシャラにどんどん書くことである。
これだけ映画もテレビもその他もあって、映像の氾濫している時代なのだから、誰だって映像のおおまかな流れ具合は頭に入っているだろう。書くための予備知識はそれで充分。あとはただ書くことだ。大事にしなくてはいけないのは骨法などではない、体の内側から盛り上がってくる熱気と、そして心の奥底に沈んでいる黒い錘(おも)りである。』
私が先にあげた6本のシナリオには正にその切実さ、熱気、錘りがあると思う。ここには確かに優れたシナリオ的感覚があるのである。
もう20年近くも前になるだろうか。ある映画シナリオコンクールに友人と共作したシナリオを出し、最終選考まで残ったことがあった。その作品はヒマを持て余しているナニワの高校生三人組のコメディで、典型的ないわゆる団子の串刺し状態で構成し、鬱屈したものを吐き出すように二人で夢中に書いたものだった。ところが、最終選考に残ったまではよかったが、殆どの審査員の方々が私たちの作品にはふれることもなく見事に無視をされた。まるで、何故こんなものが最終選考に残っているのか、といったようにである。だが、たった一人の審査員だけが私たちの作品にふれてくだすった。選評が記載された『月刊シナリオ』を無くしてしまったので、ニュアンスでしか覚えていないが、確か、「この作品には誰も票を入れないと思い、あえて最高点を入れた。(中略)これからもシナリオを書き続けて欲しい」といった同情的な内容であったと思う。だがとても嬉しかった。そのたった一人の審査員というのは山内久先生だった。この励ましの言葉は未だに胸に残っている。
もうひとつ、山内先生の言葉というか、書かれたもので、私がバイブルにしているものがある。それは『映画の創造』(映画理論講座3・山田和夫監修/合同出版)に書かれた“シナリオをどう書くか”という一文である。全部は書けないが、若いシナリオライター志望の方に向けて、その最後の部分の文を書いておきたい。
『歴史感覚は戦争世代の特権だという反論を受けたことがある。「僕たちはダランとした時代をダランと生きてきたんですからね。その実感で書きます」。とぼけるな。君も水俣の智子ちゃんの写真ぐらいは見ただろう。二十になった智子ちゃんは、母親に抱かれて成人式に出席した。吊り上がったままのあの眼は、その日もやっぱり天を見ていた。水銀に喰われた智子ちゃんの顔だけでも、あの眼一つだけでも生涯覚えておけ。
不親切ないい方になったから、もう一言だけ、心をこめて書き添える。
書くことは自分から始まる。自分を埋没させる全てを峻拒せよ。方法の問題はその次ぎに来る。』
某私立大学の映像学科の学生たちの前で、この文を読んで聞かせたことがあるが、これといった反応はなかった。それをある人に言うと、「そらあかんで。水俣病なんか今の若いもんが知ってるかいな」と一笑された。だが私は、これを読んで水俣を知ろうとする脚本家の卵が、一人でも出てくることを信じたいと思う。
最後の二行は、私は原稿用紙に書いて、しばらく壁に貼って眺めていた。貼っていたからといって、それがすぐに実行できるわけではなかった。それどころか、本当の意味が実感をともなってわかったのは、ごく最近のことであった。
この一週間、とんちんかんな日記だったと思うけれど、おつき合いしてくだすった方々、ありがとうございました。今後もただただ粘り強く、シナリオを書き続けていこうと思うだけです。
ではさようなら。