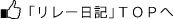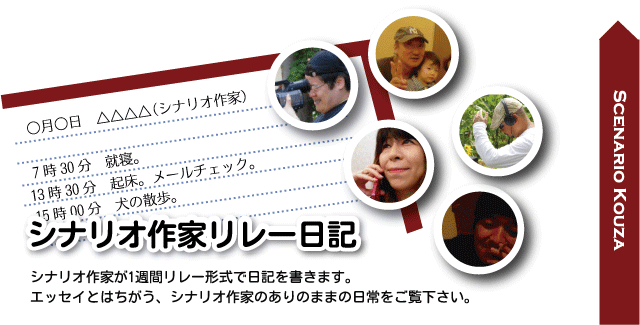2008年12月16日(火曜日)
いま、実際にあった歴史上の事件をもとにして、これまで、解釈があいまいで、その行動に謎のおおい人物に焦点をあてて小説を執筆している。
日本史上、戦国時代までは、一部、朝鮮への侵略戦争もあるけど、ほとんどが列島の中での覇権争い、もしくは、領地、つまり、利権争いであった。
明治以降、世界規模の戦争になると、必然的になんのために戦うかという命題を無視することが出来ないし、そこで、愛国心という化け物のように実態のはっきりしないものがクローズアップされることになる。
来春おこなわれるWBC、いわゆる、世界野球選手権について、一流といわれるプロの選手がかなり熱烈に日本を代表してなどと口にしたり、オリンピックなどの国際競技で国民みんなが日の丸日の丸と騒ぐのを見聞きするとき、これが、現代日本の愛国心というものの正体なのかと考えてしまうのだ。
前回にとりあげた、日本の学生達がなぜたちあがらないのか、学生運動が消えてしまったのかとの、寂聴センセイの疑問をひと言でかたづけると、国を愛するという、国民の心情が、戦後の早仕立ての底の浅い繁栄の中でまったくその本質をかえて、ただ自己満足のためという仮面をかぶってしまった。
運動というものは、全体にかかわりのある危機意識のベクトルでうごくもので、それが、生命や生活にかかわることでないと世を動かす力をもたない。政治がどうとか、北朝鮮がどうのこうのとか言っても、若い人たちの今の生き方に、世界、又、国家を意識する共有の価値観や危機感が、あるいは、夢や理想がまったくないから、運動にならない。
どこでもかしこでも、携帯電話のモニターをみながらあるいている若者達をみると、こいつらには、世界はないなとおもってしまう。
なぜ、人は戦うのか。
国のため、暮らしのため、愛する者のため――死をぜんていにした戦いにおもむく者は、たぶん、みな、その三つを心にいだいていたはずである。
第二次大戦で、なぜ、反戦の運動がおこらなかったのか。
軍部による恐怖政治のせいもあるが、米英をたおさなければ、自分達の国が、生活や家族が危機におちいるとの意識が、長年の宣撫や教育のせいだとしても、共通の危機感があったにちがいない。
集団デモゴーグというのは、極めて、危険な要素をもっているから、なぜ、学生運動がおきないのかしらなどと、見識ある大人は短絡に言うべき命題ではないのだ。
私は、いま、自分の歴史小説で、すべての人物を、なんとかっこの良い日本人がいたのだと、とり分け、若い人たちに知らしめたいと思ってかいている。
その根幹にあるのは、自己犠牲に根ざした愛である。
他人のために、アホらしいと、若い人たちは言うかもしれないが、ほんとうの愛というのは、自己犠牲からしかなりたたないはずなのだ。
文学や映画にしても、忠義、義侠、恩愛、おおくの感動的なドラマは、すべて、その魂でなりたっている。
ここで、多少、しらふに戻っていうが、レッド・クリフに不満をもったのは、三国志演義と言う明代初期のフィクションが歴史上にある魏、呉、蜀の三国の戦いをもとにしていて、劉備玄徳と関羽、張飛の三人が桃園の宴で、悪役に仕立てられた魏の曹操によって侵略された国と悪政で苦しむ民衆を助けるために、義兄弟の誓いをかわして、目的をたっせいするためには、いかなる自己犠牲もいとうことなく戦う姿に、感動し興奮して泣いたのに、その三人の描き方が、劉備は木偶の坊、張飛も関羽も見せ場はチャンバラだけ、諸葛孔明と呉の周瑜のお芝居にいたっては、私が業界デビューした東映京都の娯楽時代劇よりもっとひどいので、ああ、ああ、という感じをうけたからであった。
亀の甲を見て思いつく作戦が、何分構成かで、赤壁の合戦の変わりに無理矢理したてたにしても、もっと、ましなアイデアがなかったものか、ちょっと、俺に相談してくれたらと、ポップ・コーンをかじりながら口惜しくて、あるまともな映画人が、亀と鳩の映画かとあきれていたけれど、どんどん、今の映画のドラマツルギーは落ちてゆく、あれだけ、俺の青春の胸ときめかした、三国志に、なんということをしてくれるんや、自棄半分で、次ぎは別のほめられている作品にも、ふれてみたいとおもう。
2008年12月17日(水曜日)
実のところ、年も押しつまって、個人的なトラブルをいくつか抱えてしまって、ネットのブログというものを練習してみようかと気軽に引き受けて見たものの、どうせ埒もないご託をならべるしか能のない人間でさほどしんどくはないが、一回、二回と日記とは到底いえない脈絡のない内容になってしまって、ほんとうに、もうしわけないと思っている。
で、今日は、どうやら、今年度一番の話題作になりそうな「おくりびと」について、シナリオを志す人たちのために、ちょいと触れてみたいと思う。
なかなかの着想、題材のわりには肩のこらないタッチ、俳優さんも、ロケーションの設定も良し、美しく牧歌的な風景とチェロ――なんで田圃の真ん中でと思わせない商売じょうず、最後の石ころにいたっては、あの親父さんは女と駆け落ちしてから飯をくうときもセックスをするときも石ころをにぎっていたのかしら、それとも、臨終直前に箪笥の奧からわざわざとりだして死んでいったのか、などと、あまり考えさせないうまさと腕前、などと評価はさておき、いただけないのは、主人公の本木さん、わきとわきつれの芸達者なお二人、それぞれ、自分の過去を、映像と写真と語りで分担して観客に説明するのはいかにもお粗末です。
ドラマは、主役、つまりリードキャラクターの人生に観客を共感させて(それが否定的なものであっても)はらはらどきどきわくわくと、サスペンスをかけてストーリーに気持ちを乗せてゆかねばならない。
この映画では、主役夫婦の愛の成り行きがサスペンスだから、重要なわきつれのありよう、つまり、彼らの過去と今を、夫婦のドラマの進行の重要な鍵として使うべきで、わきつれがあっさり自分で解説したのでは、身も蓋もない。親父さんのその後の人生や、石ころのなぞも、主人公の、あるいは、その妻の推理や理解で、それがたとえ間違っていても、観客が間違いのほうを共感すれば、夫婦の共感になるから、納得し感動できる――それが、ドラマの奥行き、味わい、余韻を生むから、映画館を出た
あとにジンとくるのです。
あまり上手にはいえないけど、プロなら、あるいはプロを目ざす人ならわかってください、すこしでも。
それにしても、どうして、こんなにも、次から次へと映画が作られてゆくのか。
聞けば、上映できなくてオクラに入っている映画が六百本ちかくもあるらしい。
借金してこまっている人が大勢いるんじゃあないかな、映画なんて、殉教者的に無理をしてつくるものじゃあないとおもうけど、この不景気な時期になんなのだろう――
今日も知り合いの奥さんから電話があって、外資系の企業につとめるご主人がリストラされて、買ったばかりのマンションをてばなすらしい、ショックでね、次は、そんなことなど――
2008年12月18日(木曜日)
今日は、また、いろんなお話しをしようとおもっていましたが、私個人のことで、ちょっと手をパソコンにむけることが出来なくなりました。
とりあえず、今朝のフジテレビのモーニングショウで、キャスターの小倉さんが、デビッド・リーン監督のアラビアのロレンスのことを熱い口調で語っていましたが、何十年たっても熱く語れる映画が出てきてほしいものです。良い映画は沢山ありますが、語れる映画というものはすくない。
今週中に余裕ができたら、想いのありったけをかたりたいと思います。
と言うわけで――
ロレンス、聞き逃したけれど、どこかでニュープリントで完全版が上映されるとか、見てください。
2008年12月19日(金曜日)
つい、先日のことだが、とあるサウナで、大手の土地開発企業の中堅社員と思われる二人の男性が、自分達のプロジェクトがその地域にどう言う影響を及ぼすか、つまり、プラスの面、マイナスの面を考慮せずにすすめたから、今の行き詰まりが生じたのだと、ひとりは主張し、もうひとりは、そんなことを顧慮していたら今の会社はなかったと、企業戦略としては無用のことと反論して、かなり、激しく議論をかわしていた。
アメリカのサブプライムローンに見られるとおり、返済不能とわかっている低所得層とわかっていながら。だぶついた金を詐欺同然にかきあつめる手法は、間違いなく亡国につながる犯罪行為である。
アメリカは、世界の覇者という軽薄な自負心でおごれる愚か者である。
なりふりかまわずというが、テレビ局から発信される現今の映画興業のありかたは、まぎれもなくその類で、作品の質そのもので訴える努力を――それだけの技をもった技術者はいると思うので――しないと、かならずや、自分で自分の首をしめる結果になるのは目にみえている。
テレビ局は――やめておこう。
先日、出版業界のパーティーにまねかれて出席したが、着実にある程度の売り上げを見込める作家はもてもてで、その中に、私の後輩の藤原緋砂子さんや和久田正明さんがいて近頃、本業のシナリオの依頼がなくなった私などは少々うらやましかった。
売れる売れないの判断は、出版の世界では判断がつくらしい。クライアントの嗜好の流れがよめるからだ。
芸術を標榜して作品つくる気はないが、うれなくてもかまわないと、見栄をきってとりかかった私の小説の第一作がそろそろできあがりそうなので、自分の作品は、ひとことで言えば何なのだろうとつくづく考えている。
日本の戦国史を通じて、もっとも名高い大合戦といえば――
もっとも評判のよくない武将といえば――
私の小説の舞台と、主演者である。
2008年12月20日(土曜日)
私的なことで、夢にも自分にふりかかると思えないようなアクシデントがあって、せっかく、ブログと言うものを体験してみようと始めたのに、まことにとりとめもないダラダラ喋りになってもうしわけなく思っている。
前回で、小説のことをかいたが、ネタばらしをすると、主役はご存じの石田三成と小早川秀秋で、人間の裏切り行為を解剖的に解明しようとして、説得力をもたせようとすればするほど隘路に落ち込んで往生させられた。
もし、拙作が日の目をみたら、忌憚のない講評をたまわりたいと思う。
背信と裏切りとは根本的に違う、背信は道義的形而上的なもので戦いでは意味をもたないが、裏切りは泥臭い策略で相手の血を見ないと成立しない、つまり失敗はゆるされない即物的行為だ。
関ヶ原の合戦で、秀秋は家康に鉄砲でおどされて裏切ったなどと伝承や小説では書かれているが、それは裏切りではなく、ただ、そうしたに過ぎない。裏切りには裏切りの理念が必要である。
今回、なにを言いたいのか自分でも迷いながら書いているが、つまり、自分の利を得るために、自分を信ずる相手を騙す行為の陰湿な重さ、それが、現代の日本社会でも合理主義と言う仮面をかぶって様々な形で出てきている。大企業の契約社員の一方的な解雇通達もその一つだが、裏切り行為に、よく関係者が使う苦渋の決断という用語はない。ただの騙しだ。今の世の中、なんと騙しが多いことか。
話しはせこくなるが、身のまわりの話しで、新人脚本家などをうまい話しで誘って無償で自分の仕事(企画)の手伝いに利用しようとする業界人がおおいらしい。まあ、それも勉強、修業といえるが、仕事を依頼すれば、対価が必要である。対価のない仕事は無駄という。いま、日の目をみずお蔵入りの映画のおおくがそんな経緯でつくられた者でなければよいのだが――
次ぎの最終回は、もういちど、愛国心について、なるべくたっぷりと――。
2008年12月21日(日曜日)
だいぶん、おちついたので、少々、ながくなるが――
またまた、愛国心にこだわって――とは言っても、私は右翼でも左翼でもなく、どっちつかずのノンポリで、自分だけがそう信じる正論をまくしたてる、一番嫌なタイプの若者であった。
昭和三十年初頭の、立川、砂川基地闘争のころ、学友の一人が私を学校の裏手によんで、まず、おまえからなぐれ、そのあとでおれがお前を殴ると脅されて、相手は空手の選手としっていたから、必死のしゃべくりでごまかしてその場を逃れたのが、中学生のころに辻強盗にあっていらいの生命の危機であった。
その相手と言うのが、NHKの北米総局長をしていた日高氏で(名前もいかつい顔もおぼえているから間違いないとおもう)、強面のわりには国営放送の大幹部に治まっているのだから何てことはない。
この年になっても、映像と文学という殴り返されても貧乏するだけの最高の表現手段をもつ私の勝ちである。
若い頃は、イケイケでよかった。
年をかさねると、お寺や神社でおいのりをすると、まず、世の中、つまり、世界のことがらに手をあわせるようになってくる。
人間は国ではしばられていない。しばられているのは、民族である。
民族とはなにか。いやおうなしに、互いをしばりつけている血である。
だが、その血が、時として、人間生存のアイデンティティへの大きい障害になる時がある。
ここに、その歴史的なモデルがある。
ある人に企画をもちかけられて、どんなことがあっても、日本人として、これは実現しなければならないと思い、天台宗米国ハワイ総局長の荒了寛師やハワイ日系一、二世のご協力をえて、取材をかさねて、まず、小説からとりかかることにした。
私ごときが筆にするのもはばかれるような、感動的な歴史の事実である。
この日記の終章に、その中味の一端を皆さんに披露したいと思う。

天台宗米国ハワイ総局長の荒了寛師
■四四二パイナップル・アーミイの奇跡、企画書
愛国心の正体とはいったい何なのか。今、日本人として、自分自身に問いかけて見ても明確な答えをつかむことができない。ましてや、戦争体験のない若者達には、曖昧模糊とした感覚的なものでしか無いのではあるまいか。では、オリンピックや野球などの国際的なスポーツで日の丸の旗がたかだかと掲げられた時のしびれる様な感動は、一体、何なのか、あれが愛国心と言うものの正体なのか、いや、そんな生やさしい代物ではないはずだ、場合によっては、自分の意思に反して、命を捨てなければならない、その代表的な事例が戦争である。その場合、自分の行為を正当化し、納得させる魔性の物、それが愛国心であるとすれば、その正体が何なのかと言うことを、真っ正面から問いかけるのが、この映画である。
第二次大戦時におけるアメリカ日系二世三世達によって編成された、四四二戦闘部隊、ハワイ出身者が多かったことから、アメリカ人からいささかの揶揄をこめて、パイナップルアーミイと呼ばれた兵士達の戦いの軌跡をたどると、その答えが見えて来る。彼らが突きつけられた問題、自分は日本人なのか、アメリカ人なのか、つまり、人間にとって、祖国とは何なのかと言う大命題を解かないかぎり、愛国心の正体は見えて来ないのだ。
第二次世界戦争で、日本とアメリカが戦争状態に入った時、彼らは自分達の生きる権利と、その心のよりどころを、彼ら自身の存在の根源に拘わる問題として突きつけられた。 祖国とは、身体に流れる民族の血で決まるのか、あるいは、異境の地であっても、そこに根付いて、家族を養い子供を育てた土地をそう呼ぶのか――単純な様で、実に、複雑で難しく選択に困る問題である。日系米国移民の歴史は主に明治時代から始まっているから、第二次世界戦争当時の若者達は、日本語すら知らない三世と呼ばれる世代で、生活文化習慣そして感性や思想までもがほぼアメリカ人そのものであった。中でも、ハワイは日系移民が全人口の半数近くを占めていたから、若者達は当然アメリカの市民権を持ちアメリカ人と思いこんで生活していたのだが、日本軍がハワイの真珠湾に集結するアメリカ太平洋艦隊に奇襲攻撃をして一方的に宣戦布告をしたその日から、彼らの境遇と運命は一変したのである。つまり、昨日まで仲の良かった隣人達から敵視され、差別と警戒心が露骨になり、アメリカ本土に住む日系人などは、父祖代々、苦労して手に入れた土地や財産を没収されて収容所に監禁されることになったのである。民間人に限らず、すでに、アメリカ軍人として兵役についていた多くの日系の若者達も軍隊内部で白眼視され差別を受けた。ところが、ハワイだけは微妙に事情が違っていた。日系人が全人口の半数近くを占めていたから、日系であると言うだけで孤立することも無く、アメリカ当局としても、ハワイの日系人を全員収容所に監禁したら、ハワイから住民が消えて死の街になる恐れさえあったから、表面的な生活に変化はなかった。早く言えば、それだけ、その土地に同化していたと言うことであって、戦争が長期化して日系の若者までも徴兵する必要に迫られたとき、ハワイから驚くほど多数の日系の若者達の応募があったと言う事実がそのことを証明している。
ハワイの州兵部隊には、戦前から、日系二世の、第百大隊と呼ばれる部隊があって、ヨーロッパ戦線で、ドイツ、イタリア軍との戦闘できわめて優れた戦果をあげていたから、戦争が長引くと、前線司令部から、日系部隊を派遣する様にとの強い要請がなされるようになった。かくして、第二次大戦を通して、最も勇敢であったと讃えられた、四四二大隊、パイナップルアーミイが誕生したのだ。
基より、彼らとて、自分の身体に流れる血が日本民族のものであることを知らない訳ではない。日本を敵にして戦うことに強いジレンマを感じ無いはずがなかった。しかし、そのジレンマは、彼らの親、そのまた親達と、世代が変わると、また、微妙に違っていた。地域、友人、身内、職場、あるいは夫婦、恋人、それぞれに、様々な心の葛藤や食い違いがあったに違いない。しかし、究極の選択として、彼らを敢然と対日戦争にむかわせたのは、自分達の先祖に土地と仕事を与え、自分達が生まれ、自由主義の名の下に生活することを認めてくれたアメリカへの恩義と、そして、自分達の土地と生きる権利を子孫のために守ろうとする、強固な意思であった。実際の戦闘で、きわめて危険で無謀と思われる作戦に向かって行く時に、
「ゴー、フォー、ブローク!」
と言うフレーズを合い言葉にして、彼らは任務を遂行した。当たって砕けろと訳されているが、何も得るものの無い突撃、報われない突撃、そう思える戦いこそ、真の勇者の誇りだと、そう信じて、彼らは一歩も退くこと無く戦いに挑んで行った、その死の献身があってこそ、アメリカと言う新しい祖国が、彼らを認めてくれると信じていたからであった。 彼ら自身は気付いていないかも知れないが、そこに、我々は、死を前にした時に、百倍にもなる闘争心、使命感、連帯感、つまり、日本人特有の、戦士としては優れているが、きわめて悲劇的な特性を見ることが出来るのである。
近年、硫黄島の攻防戦を描いたハリウッド映画が日本で公開されて大ヒットしたが、日本の過去に、あんな悲劇があったのだと言う事実を若い人達に教えた意義は大きかったと思う。しかし、外国人の描く日本の軍人は、あまりにも死に対して短絡で感傷的で、心をえぐる様な感動はなかった。平凡なメロドラマに仕立てた作り手の作劇術にも問題があると思うが、やはり、あの出来事は圧倒的な軍事力のアメリカに、徒手空拳の日本軍が弱い者いじめの様に殺されてゆく話しであるから、辛すぎる。
この、四四二大隊の話しは、その意味で、見事に勝つ話しである。勿論、犠牲者は信じられないほど多数にのぼった。しかし、涙に濡れ、合掌しつつも、おもわず、拍手し喝采を送りたくなるような、実際にあった、素晴らしい記録なのである。
なぜ、今、この出来事を映画化するのか、それは、ひと言で言って、ほんとうの、人間愛とは、どう言う状況で生まれるかと言うことを、観客、とくに、若い人達に見せたいからである。そして、日本人であることの、誇りと歓びを与えるためである。
本来、ストーリーの末尾に書くべきエピソードであるが、この映画を作る真の意義を理解していただくために、矢野徹氏の労作、「442」の最終章を、ここに、そのまま紹介して、企画製作意図をしめくくることにする。
「一九四五年九月二日、東京湾に浮かんだアメリカの戦艦ミズーリ号上で降伏文書が調印されているころ、アメリカの首都ワシントンで戦勝記念日の閲兵行進が行われていた。ヨーロッパ派遣アメリカ軍各部隊が、軍楽隊の勇壮なマーチに乗って堂々と行進して万雷の拍手と歓声は全市を埋め尽くすほどであったが、その拍手と歓声が、突然、消えて、大通りを埋め尽くした大観衆がシンと静まりかえった。かれらの目の前に、いま行進して来るのは442連隊戦闘団だった。前の隊との間隔が大きく開いていた、それは、あまりにも少ない人数であったからだ。巨体のアメリカ軍人と比べて貧弱で小柄なその兵士の集団こそ、アメリカ合衆国陸軍、いや、全三軍の中で最も勇敢に戦い最も多くの死傷者を出した部隊であり、いま目の前に現れたことを、人々は知ったのだ。 かれら日本人の二世達が、日系アメリカ人がその命をもって尽くしてくれたことに、我々はいったいなにを報いて来たのだ――ユダヤ人を強制収容所に入れたナチの蛮行を非難する資格があるのか――すべてのアメリカ人の胸を突き刺す様な痛恨の思いと共に熱い感動が沸き起こって来たのだ。一人の男が帽子をぬいだ。みるみるうちにすべての人が帽子をぬぎ傘をたたみ、隊列の中に目に見えぬ戦死者を見たかの様に敬意と哀悼の意を表した。その時、静まりかえっている人々の中から、一人の老婆が泣きながら叫んだ、「坊やたち、おかえりなさい!」
日系二世兵士の母親なのか、祖母なのか――
「ワアッ!」
その声を導火線にして、全市をどよもす万雷の拍手と歓声がまきおこり、それはいつまでもいつまでも続いた。すべての人が目に涙を浮かべて手を叩き続けた。 大統領の前を歩くタムラ少尉の胸に、死んで行った戦友達の姿が次々と現れては消えていった。
「きみたちの死は、むだでは無かったんだ、きみたちと共に戦った思い出を忘れず、おれ達はより大きい未来にむかって歩いて行くんだ」
部隊の先頭、胸をはって歩くタムラ少尉の目に涙は光っていなかったが、その胸中には、戦争と言う人類が繰り返す愚かな行為に対する激しい怒りと、祖国と家族を守るために堂々と戦い死んで行った多くの友への惜別と称賛の思いが複雑に渦巻いていた。
■「ストーリーの概略」
タムラ、つまり、田村高史は日系の三世である。一家はハワイで小さなパインアップル農場を経営している。祖父は明治時代に日本から移住して来て、すでに故人となり、その妻である祖母アサと、父親幸助、母親正子、弟勝史、妹ゆきの六人家族である。一家の生活は決して楽ではなく、田村は口減らしの意味もあって、弟に父親の手伝いをさせて州兵に応募して、軍人になる道を選んだのであった。映画はこの家族を物語の主軸として展開してゆく。
一九四十年十二月の早朝、田村家の生活は一変する。幸助と勝史が農場で頭上すれすれに日の丸の戦闘機が飛来するのを見た数時間後、田村は兵舎で、仲間の兵士達と白人下士官達の襲撃をうけて監禁された。
「日本とアメリカが戦争」
信じられないことが起こったのだ。
まず、彼ら日系人と現地のアメリカ人達との生活に大きい変化があった。ハワイでの生活に差別は無かったのだが、どこへ行っても突き刺す様な視線が飛んで来た。妹ゆきがからまれ、隣家の岡本青年が庇って殴られた。怒る田村を父幸助がいさめた。いま、暴力をふるえば、これから、一家は生きては行けない。
彼ら、日系青年達の心の救いは、ハワイ出身の先輩達、第百大隊のヨーロッパ戦線での活躍であった。その実績もあって、州兵部隊がアメリカ本土に行き、実戦の訓練を受けると聞いて、田村達は喜んだ。だが、日本を相手に戦うことには、家族の中で微妙な意見の違いがあった。祖母アサが言った、
「アメリカに恩返しをしろ」
このひと言が田村の決意の後押しをした。
アサの夫、つまり、田村の祖父は、旧上杉藩の下級武士で、先妻の子を連れてハワイに移住し、アサは写真見合いで祖父と一緒になったのであった。
「会って見たら、写真とは違ってちんちくりんの風采の上がらない男で、がっかりしたけど、気っぷの良さが気に入ってね、他人のためなら、我が身をけずっても面倒を見る、だから、ずっと、貧乏――」
アサは、田村が祖父にそっくりだと、だから、商売には向かないと、軍人になることを勧めたのであった。
「戦死でもしたら」
母やゆきが心配したが、私の可愛い孫だもの仏様が守ってくれるよ、と、アサはケロッとして言った。勝史は兄を慕っていたから、志願したがったが、田村が許さなかった。田村には恋人が居た。名はジェーン、小学校の教師をしていて敬虔なクリスチャン一家の長女であった。ジェーンは真珠湾を不意打ちした日本を憎みながらも、田村や一家には何の関係も無いと言ったが、田村がなぜかこだわりを持ち、別れに際しても会おうとはしなかった。岡本も志願した。岡本は母と二人暮らしで詩を書く心優しい青年であったが、母は潔く一人息子を送り出した。
「父ちゃんも、きっと、行けと言ったよ」
岡本の父親は早くに死んでいた。出発する田村に、アサは夫が大事にしていた小さな念持仏を与えた。
田村ら州兵と岡本ら志願兵達は、ミシシッピーのキャンプ・シェルビーに送られて訓練を受けることになった。キャンプには、アメリカ本土からの日系の二世の志願兵も居て、中には、夫婦二人でアメリカに移住して来てやっと自分の土地を手に入れた途端戦争になり土地も家もすべて接収された不運な境遇の者も居た。
「手柄を立てたら、家と土地を返してもらえるかも知れない」
川島と言う実直そうなその男の志願の理由は切実であった。
訓練はベテランと志願兵も一緒くたで、白人、有色人種、日系が入り交じっていたが、日系人の成績が圧倒的に優秀であった。だが、ここでの差別はハワイどころでは無かった。訓練で汗を流したあとも、田村達は酒保でいっぱいのビールを飲むことも許されなかった。こっそり飲もうとした小柄で剽軽者の鳥山らがテキサスの大男ダンカンらにボコボコにやられた。田村らは殴り込みをかけた。巨漢揃いのテキサスグループに田村達は返り討ちに合いかけた。韓国人(当時は日本人)の金少尉が田村達に加勢して形勢は逆転した。ハンプステッド大尉(中隊長)が割って入って。仲直りの乾杯をさせた。田村とダンカンのわだかまりが消えることはなく、ジャップとののしられて、又、喧嘩になりかけ、ハンプステッドがダンカンを激しく叱った。
苦戦の続く、ヨーロッパ戦線から、日系部隊の早期の派遣の要請が来ていた。太平洋戦線とは違って、直接、日本軍との交戦の無いヨーロッパでの参戦は、田村達にもさしたる抵抗は無かった。田村達、ベテラン、新兵混合の日系二世部隊は、ペンス大佐率いる一個連隊に編成されて、イタリー戦線モンテ・カッシーノに駐留する第百大隊の所属する精鋭三四師団に配属されることになって、アメリカ本土を離れた。
(ここまでを、映画の三分の一で描く)
イタリア、カッシーノでの奮戦ぶりは、様々、記録にのこっているが、戦争の状況の説明も合わせて、写真やニュースフイルムで描写する。そこでの、激戦ぶりを伝えるには、ヘルメットの代わりに毛糸のスキー帽で最前線でも通した金少尉のダンディズムや、常に、先頭に立って指揮したペンス連隊長の勇気など、あまたのエピソードがあるが、勇猛に戦った四四二部隊の中でも、田村の中隊が何ヶ月かの間に半数になり、上官が悉く戦死をして、いつしか、田村が、自動的に中隊の指揮を執る様になっていた事実が、その過酷な戦闘の状況を如実に物語っている。また、一方では、本土やハワイからの家族や恋人からの便り、イタリア女性との淡い恋などのエピソードも描いて、比較的、肩の凝らない中幕でのこり半分のクライマックスに持って行きたい。
さて、いよいよ、本映画の最大の見せ場で、四四二の名を世界に知らしめた戦いになる。
「失われた大隊」
ドイツが降伏する前年、スイスの北西、ドイツとフランスの国境地帯のボージュ山岳地帯にある、機甲師団を含むヨーロッパ最後で最強のドイツの防衛戦線に、アメリカ軍が総攻撃を加え、苦戦が続き、テキサス一四一歩兵連隊がドイツの大軍に包囲されて完全に孤立してしまったのであった。アメリカ軍は何度となく救出作戦を試み、兵器や糧食の空中投下を行ったが悉く失敗に終わり、見捨てざるを得ないとの悲痛な空気が司令部に流れたのであった。このニュースがアメリカ本国に流れると、テキサスの在郷軍人会や政治家、兵士の家族、一般市民から大統領に激しい抗議が殺到した。作戦の責任者ダルスキー少将は、ついに、ペンス大佐に、四四二大隊の投入を命じた。ペンス大佐は猛然と抗議した。四四二は、すでに、ヨーロッパ戦線で最大の被害を出していて戦闘に参加出来る状態では無かったのだ。田村は少尉に任官していて、二百人の大隊の指揮官であった。そこへ、思いも掛けず、負傷して後方に下がっていた金中尉が戻って来たのだ。田村は驚いた。金は本国に送還されるはずであったのだ。金はハンプステッド大尉が戦死をしたと言った。金とハンプステッドは、ミシシッピーのキャンプでの喧嘩以来、深い友情で結ばれていて金は仇を討ちたいと言った。ハンプステッドはテキサス一四一連隊の大隊長であった。あのダンカンも失われた大隊に居るかも知れない。田村は、カッシーノでダンカンと再会して、別々の戦場に別れる時、ダンカンは、友よ、ニホンのサムライよ、と乱暴に書いたバーボンを田村に届けてくれたのであった。田村のまわりには、岡本や川島、鳥山らがまだ無事な顔を揃えていた。これまで、危ない作戦になると田村が庇って来たのであった。皆の同意を得て、田村はペンスに特攻攻撃の志願を申し出た。
「自分らが、戦っているのは、アメリカのためだけじゃあない、何十万もの、日系人のためなんです」
川島が言った。ペンスは泣いた。とっておきの酒を出し他のアメリカ将校も来て田村達の無事と作戦の成功を祈った。
師団は田村達四四二の特攻作戦の全面支援をしたが、ドイツ軍の抵抗は予想をはるかに上回るものであった。
田村の副隊長格の金が壮絶に戦死した。田村は大隊を分散して、テキサス大隊を包囲しているドイツ軍の背後に迫った。突然、ドイツ軍の斥候部隊と遭遇して、鳥山が、敵だ!と叫んだ。日本語を知っているドイツ兵が、日本軍が助けに来たと喜んだ。田村達は斥候部隊を倒して危地を脱した。
ここからの壮絶な戦闘は、いま、このストーリーでは描ききれないが、川島が、被弾して死ぬ前日、妻と子供の写真を田村に渡して、言い残した、
「ぼくが言うのもなんだが、気だての良い女だ、器量もわるくない、できたら、隊長殿みたいな人と、新しい生活をしてほしい」
田村は、川島らと酒を飲んで、一生結婚をする気は無いと言ったことがあったのだ。田村は写真を胸にしまった。
田村達は、ついに、テキサス大隊の何百人かの生き残りを救出した。一日遅ければ、全滅するところであったから、隊員達は驚喜して田村達を迎えた。ダンカンが居た。誰かが、ジャップに助けられるとはな、と、吐き捨てる様に言った。その兵士は、ダンカンに死ぬほど殴られた。
岡本は奇跡的にぶじであった。岡本は最後の攻撃の前夜、自分は死ぬ様な気がすると言って、ゆきに渡してくれと自分の詩集を田村に預けようとした。田村は怒って受けとらなかった。アメリカの空軍機が来て、食料や水を投下した。アメリカ兵達は歓声をあげて我がちに拾おうとしたが、田村達は動こうとしなかった。疲労だけでは無かった。二百人いた大隊が、身動き出来る者がわずか七八人、生きている者は三十人たらずしか居なかったのだ。達成感と言うよりは、田村は、強い空しさに襲われていた。岡本は詩集に挟むために山の尾根に咲く名も知れぬ花を手折ろうとした。地雷が爆発して、岡本は、詩集だけを残してこの世から、消えた。
「ボージュの森に帰らぬ友よ
ともに戦いし想い出を胸に
われらまた大いなる未来に歩まん
さらば友よ、友よさらば」
田村は、祖母の念持仏を、この激戦の丘に埋めた。
いま、田村はワシントンの大通りを、嵐の様な歓声に包まれて堂々と行進している。
その中に、金が、岡本が、川島が、ハンプステッドが居る。
ハワイに帰った田村は、祖母アサが自分の出征中に死んだことを知った。病気になっても医者にもかからず薬も飲まなかったらしい。
「きっと、自分の命、仏様に捧げて、兄ちゃんを守ったのよ」
ゆきは、岡本の戦死を知っていた。田村はゆきに岡本の詩集を渡して、すぐに、アメリカ本土へ向かった。ジェーンが来たが、田村は会おうとしなかった。勝史がジェーンをなぐさめた、
「いまは、そっとしておいてやってください、 きっと、帰ってきますから」
テキサスの田舎。川島の妻子が暮らす小さな家があった。田村は農機具を持って、荒れた土地の開墾を始めた。鳥山が、ダンカンが来た。明治の世、初めて、移民として自分達の土地を持つため、夢を耕し種をまいた、一世開拓移民達の様に、汗を流して黙々と鋤をふるう。
――――――
日系兵士にかぎらず、この物語には、多くの米国軍人も登場する。いずれも、実在のモデルがあるが、すべて、彼らへの、限りない敬意をもって、フィクショナブルに創作を加えてある。
この映画は、決して、愛国心を昂揚するものではない、人間愛のすばらしさを、心から賛美するためのものである。
終わり
文責 高田 宏治
この最終章をかく直前に、NHKで、身空ひばりさんの全盛期の「悲しい酒」をきいた。 まさに、絶唱である。
感動とかなんだとか、言うのもはばかれる魂の技である。
一人の歌い手が、また、作詞、作曲家が、これだけの芸術的作業をやってのけるのだから、われわれは、なにをしているのかな――?